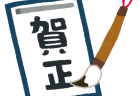久野先生へのインタビュー 最終回 fj特別編
1984.3 東京工業大学理工学研究科情報科学専攻博士後期課程 単位取得退学 1984.4 東京工業大学理学部情報科学科 助手 1986.3 理学博士(東京工業大学) 1989.4 筑波大学大学院経営システム科学専攻 講師 1990.8 同 助教授 2000.12 同 教授 2016.4 電気通信大学情報理工学研究科 教授, 筑波大学 名誉教授 2022.4 電気通信大学情報理工学研究科 特命教授
久野先生は、2016年に本学教授として就任され、一年次必修科目「コンピュータリテラシ/基礎プログラミングおよび演習」のカリキュラム作成に尽力されました。長年、プログラミング、ユーザーインターフェース、情報教育の分野をご専門とされ、情報の教科書なども執筆されています。詳しくは先生の個人サイトをご覧ください。

先生がインターネットを始められた最初の頃のネットニュース fjと呼ばれるものについての思い出とか印象深い出来事があれば教えてください。
例えばX(旧Twitter)では運営というのはプロがやっていますが、fjの中ではそういう管理というのは全然ないですから、ニュースグループ管理委員会とか自発的にやりたい人が出てきて、総合選挙をやって、そういう風なネットコミュニティの始まりというのはいろんなことをそういう風にやったので、それは面白かったですね。それから私がハマったのはfj.soc.smokingで、喫煙する時にタバコ吸いたい人は吸いたいけれども、吸わない人にとっては害があって、そういうことをどうするかは議論はずいぶんあったんですけども、そこはいろいろ議論をして、最後はオフラインミーティングまでやったりしたんですね。そういうのは非常に面白いから、自分の昔の思い出というか懐かしいというか、そういうのがありました。
先生はこのfjでニュース管理委員会の委員とかも務められていらっしゃいましたよね
それは毎年改選があるので、その中で3期ぐらい委員やったことはあるんですけども、委員といっても事故は普通なかったので、だいたいどういう風にしますかとか、どういうところはどういう方針にしますかとか、方針の文章はこうしますかとか、そういうのは普通の議論ですよ。だから皆さんが、雑誌や学内広報を作るとかみたいな感じかな。
先生が務められたってことはやっぱりfjに愛着というかなんかそういうものがあったのですか
それはもう非常にありました。ただfjのニュースフィードがやっぱり供給がなかったので、それで今は参加してないですね。ちょっと残念だとは思います。
-fjは、98年、2000年前後ぐらいまでだいぶ勢いがあったと思うんですけど、その後2ちゃんねるとかが勃興してきたわけじゃないですか。2ちゃんとfjのどちらかというのはありましたか
2ちゃんねるもありましたね。2ちゃんねるには自分のアイデアとか、そういう意見を書き込むことができた、というのもありました。ただ、2ちゃんねるでは、料理とか、その一部の人たちが専門家としてどんどん自信をつけていったりとか、そういうのは自分には及ばないな、とかもありました。だから、全部自分たちで作り上げていくというのは、純粋に面白かったけど、2ちゃんねるの、多種多様な人がいるとか、強力なサポーターがいるとか、そういうところはすごいなと思っていました。
fjのアーカイブを見ると先生がRubyの作者である松本ゆきひろ先生と交流を結構とられていたなと思うのですが、この経験がRubyをカリキュラムに組み込むことに影響しましたか?あるいは、Rubyに特別な思い出などありますか?
僕がfjをやっていたころの松本さんって、最初は院生ですよね(まつもとゆきひろ氏より当時は学部生であったとの訂正をいただきました2)。 だから学生さんの一人で、普通にお話はしたけども、そんな特に変わったことはなかったですね。Rubyっていう言語を作ってみた3とか、それは色々言語を作るという人はいるので、まあ普通のこと。そういう意味では、学生時代の松本さんからは何かってことはなかったですね。ただ、Rubyという言語を自分で作って様々なところに広めていって、その努力がすごいと思うし、僕が知ってから松本さんと様々にお会いしたり話し合ったりする上で、そういうことは非常に尊敬を感じていました。松本さんの方は、僕のbitの連載でCLUっていう言語についてさっきお話しましたけど4、CLUの話とかで結構気に入ってくれて色々と話をしたので、そういう意味では松本さんとの交流はありましたね。ただ、それが決定的だったということはなくて、スクリプト言語で、Rubyの頃は、RubyかPythonか、Perlなどと比べてRubyはさっきの話の通り、書きやすい、型がなくて、しかもendがあって、様々なオブジェクトを自由に、必要に応じて書きやすいという意味では、そういう意味で言語そのものの良さからRubyを選んだというふうな気がします。
実は、Rubyを使って、東京大学で非常勤で担当した入門科目があったんです。その時、東京大学のRubyコミュニティの、笹田耕一さんという方が着任され、一年で教育をRubyで行う授業改革をされたことがありました。私は当時、非常勤でやっていましたから、彼に賛同して一緒にRubyによる入門科目を始めたのです。それがうまくいったので、伝統的に残っているというのがあります。
アフタートーク
インタビュー後の雑談をまとめました。
LLMの話で、AIがここまで、例えばChatGPTなどはここまでできて、そこから上が人間のできる領域、LLMができない範囲の課題を出していこう、というようなお話をされていました。5今後授業するにあたって、そうなると生徒側の知識の認識のアップデートに加えて、教員側の認識、教員側もそれを理解した上で課題を作っていかなければいけないのかなと思うのですが、そうなると教員側の認識、教員側も勉強していく必要があるのかな、ということが気になりました。
そうですね。コンピューター自体でやっていた目標などは、自分の頭で考えて自分でいろいろ工夫してやる、というふうに変わっていくわけですから、それをサポートするためにLLMをどう使うか、ということが重要だと考えています。そのような方向に進むのは良いことです。世の中の勉強の中には、すべて暗記した方が簡単だ、というようなものが多くあります。そのような暗記するだけのつまらない勉強はどんどん淘汰されていくでしょう。電通大では、そのようなものではなく、やはり自分の研究に関係して、面白い勉強をしていくというふうに思っています。そのようにこれから世の中が変わっていけばいいなと思いますね。
僕自身、大学に入るまで一切家にパソコンがありませんでした。大学に入ってから初めてパソコンに触れ、プログラミングにも触れていったんです。その中で、「コンピュータリテラシー」と「基礎プログラミング」の授業は、僕にとって情報教育の初歩的な部分、そもそもプログラミングに触れるという点で、すごく助けられました。小さなコンピューター、Ruby、Cといったものを、序盤の段階、1年生の段階で教えてもらえたことは、すごくありがたいなと思っています。
ありがとう。私の「コンピュータリテラシー」や「基礎プログラミング」の演習の中で、どういうアルゴリズムや、どういうことを教えるかというのは、結局、私が学んできた様々な科目の中から組み上げてきたものです。こういうことは満足とかいうのが、合わせてできると。つまり、私が用意したものは、私が学生として学んだものから来ているということです。私が学んだものを皆さんが受け取ってくれ、そして、皆さんが他の人に教える機会には、そういうエッセンスがもたらされていく。そうやっていかないと、どんどん学ぶ内容が増えてきて大変なんですよね。色々な知識が増える一方なのだから、自分の大事なエッセンスを絞っていって、それに新しいものを加えていくということをしていかないと、人間は進歩できないんじゃないかな。そういう流れの中で、授業というのはできているんだと思いますね。
先生がSNSを通じて発信されているっていうところが、先生をインタビューするきっかけだったんですけども、なかなか普段では聞けないお話を聞くことができて、非常に我々としてもいい機会になったかなと思います。
私としても、こういうお話をするっていうのはあんまり機会がなくてですね、X(旧Twitter)では書けることっていうのはほんの少しなんで、こういう今日みたいなまとまったものをお話しさせていただくっていうのは非常にいいことだったと思うんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。一応質問としては一通り終わってるんですけども、もし先生の方から何かあれば。
授業は生き物であって、本当はどんどん改善していかなければならないけれども、僕はもう引退してしまったから、次の人が僕が作った授業を元に何かっていうのはまた続いてほしいなっていう気持ちがあるっていうのが、一番ですかね。
編集後記
この度、久野先生にはお忙しい中、2時間にもわたるインタビューのお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。結果的に長時間となりましたが、先生ならではの視点から、数々の貴重なお話を伺うことができ、大変実りある時間となりました。特に、ただ履修するだけでは知ることのできない教材制作の意図などについては今後の学習に大いに役立つものと確信しております。本シリーズが、来年以降も新入生たちの参考になることを願っています。
しかしながら、インタビューから記事掲載までに時間を要してしまいました。これは、ひとえに私の不徳のいたすところであり、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。そのような中でも久野先生には、未熟な我々の拙稿に対し、迅速かつ的確なご校閲を賜りましたこと、重ねて御礼申し上げます。先生の細やかなご指導のおかげで、記事の質を格段に向上させることができました。
久野先生には、この場をお借りして改めて感謝を申し上げますとともに、今後一層のご自愛をお祈り申し上げます。
- :https://uec.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000703769707421&context=L&vid=81UEC_INST:UEC&lang=ja&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
↩︎ - https://x.com/yukihiro_matz/status/1874085965326934405 ↩︎
- Rubyは1995年12月21日,fj.sourcesにてver.0.95が初めて公開されましたhttps://groups.google.com/g/fj.sources/c/bCc2JimcmAo/m/ONqCnbyG7LMJ ↩︎
- https://www.gunjyo.gakuyukai.uec.ac.jp/hp/wp/post-373/ ↩︎
- https://www.gunjyo.gakuyukai.uec.ac.jp/hp/wp/post-384/ ↩︎