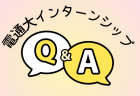電通大インターンシップ推進室 ~学生と企業の窓口~
インターンシップのあれこれをインターンシップ推進室の先生方にお聞きし、インタビューさせていただきました。
全4回の構成を予定しており、第3回である本記事ではインターンシップ推進室のお仕事についてお話しいただきました。
インターンシップ推進室のお仕事
一歩踏み出す勇気を支える、インターンシップのサポート
古川先生:直接的なインターンシップというよりも、大学で学んだ主にエンジニアリングに関する知識を企業でどう活かせるのかを支援するためのインターンシップのお手伝いをしています。
国際インターンシップのように準備に時間がかかるため、1年前から準備を行うといった事例もありますが、国際インターンシップの場合でも、年度が変わる3月から4月ごろから相談に来る学生が多いです。
国内のインターンシップの場合も同様で、年度が変わる 4 月ごろから推進室に相談に来る学生が多いです。その時に、単位としてのインターンシップの流れや、企業からの情報をお伝えするというところからまず始めていきます。また、単位履修としてのインターンシップの相談を受けることだけではなく、夏休みにプライベートで参加するインターンシップの相談や、エントリーシートの確認依頼なども、できる範囲で対応をしています。現在は、ちょうどインターンシップが終わって皆さんに報告書を書いてもらっている時期です。報告書が出てきたら、その報告書を見て必要に応じてフィードバックをして、いただいた報告書を学内の中の会議に色々と諮っていくのですけれども、このような仕事も私たちで担当しています。そのため、1 年を通じて特に忙しくなるのは、新年度から夏休み頃までで、皆さんのインターンシップの準備のご支援とインターンシップを実施している期間のフォローアップが主な業務となります。後期になると、私たちは主に事務作業や関連活動を行います。
インターン後の支援について
古川先生:直接的な就職支援となると、東2号館の1階にあるキャリア支援センターの就職支援部門が主担当となります。ただ、我々も似たような仕事は行っているので、「担当が違うから来るな」ということは望むことではなくて、 インターンシップの中からの流れで対応もしています。
10日間というインターンシップの期間について
電通大の未来を創るインターンシップ基準
古川先生:規則的な面で言うと学習要覧に書いてあるから、というのが理由です。皆さん、 入学時などに学習要覧というハンドブックをもらうと思います。ホームページでも公開されていて、それぞれの授業の目的や内容が記載されています。特に、学域のインターンシップカリキュラムのところに書いてありますが、コースツリーがあり、そこで最低10⽇間、90時間以上の実習をすることが決まっています。これは勝手に数字を変えられるわけではなく、大学としてプロセスを踏んで決めたものです。電通大としてポリシーがあり、10⽇ 90 時間と決まっています。
電通大として、インターンシップでスキルを学ぶ上で 10 ⽇間は必要と考えています。
インターン推進室設立の経緯
古川先生:電通大としてキャリア教育の重要な機会と位置づけているインターンシップは、 98年度から行われています。これは国内の事例として早い方だと思いますが、私が電通大生だった30年ほど前にも、工場実習だとか、企業訪問をして、実際にどういうことをやっているのかを見せて頂く機会がありました。教育の現場と実際の企業の現場をつなげるということが、電通大では昔から良く行われていたと思います。無線通信士を養成する無線電信講習所が1918年に創設されたことが電通大の原点ですので、その思いが今でも続いているのではないでしょうか。
インターンシップの背景:政府と経団連
古川先生: 「インターンシップの推進にあたっての基本的考え方」、通称「三省合意」というものがあります。これは、インターンシップに関係する3つの省庁、具体的には文部科学省、厚生労働省、経済産業省が関与しています。この合意では、インターンシップの進め方に関するガイドラインが示されています。ホームページなどから検索すると、詳細が出てきますが、この合意の中でインターンシップの考え方が取りまとめられています。
しかし、政府が勝手に決めたわけではなく、経団連が自ら議論し、インターンシップはこうするべきだと公表した報告書の内容が根底にあります。この経団連からの報告書では、1day や会社見学自体を否定するわけではありません。しかし、インターンシップと名のつくものには一定の基準を求め、少なくとも5⽇間以上は行うべきだということが示されています。また、理工系の学生に求められる専門能力を活かしたインターンシップといったものであれば、少なくとも2週間の実施を求めています。このように、インターンシップとして実施をするのであれば、しっかりと期間をとって経験を積むべきだという立場が取られています。
短期のインターンシップ
大堀先生:クラスルームから、単位認定にはならないけどもこういったインターンシップの募集がありますよという案内が来ると思います。このような案内をその都度行っています。ただ、企業のインターンシップ全てを網羅しているわけではないですし、自分自身で気になる企業のインターンシップを調べて応募している学生も多かったですね。自分の行きたい業界や業種を調べて、公募の場合はエントリーシートを書いて、書類通過をして、面接に受からないとインターンシップへは行けません。そのため、いくつもの企業の選考と並行して行っていたり、10⽇間の大学推薦企業でのインターンシップを進めながら公募を何社も受けていたりという場合もありました。インターンシップへの気持ちが高ければ高いほど、行動力があればあるほど自分で調べて、いろんな情報を網羅しながら行動しているのだと思います。
推進室の方からのメッセージ
インターンシップ推進室が未来への道しるべになります
大堀先生:インターンシップ行く前の段階、面談の段階で、自分で全部考えてこなきゃとか、 いろいろやらなきゃいけないけど何すればいいか分からないといった迷っている状態で来る学生さんも多いですが、自分の中で迷わずに、分からないことがあればインターンシップ推進室に何でも相談に来てほしいなと思っています。誰に相談していいか分からない、という状態でさまよったままの状態の学生さんも結構いたので、インターンシップ直前でもいいですし、インターンシップ前のエントリーしようか迷っているという4月の春の段階でもいいです。平日月曜日~金曜日までインターンシップ推進室は空いていますので、いつでも相談に来てもらってもいいと思いますし、過去の先輩たちがどんな風にインターンシップしたのか、どんなところに行ったのかをまとめた報告書があるので、授業の空きコマの間に見に来たりだとか、そういう形でインターンシップ推進室を自分の今後のキャリアを考えて、いくらでも活用してもらえたらなと思っています。
古川先生:本当に気楽に来てください。例えば、来年度3年生になるから単位履修したいです、という人はもちろんウェルカムですけれども、特に国際の視点でいうと1年生だとか2年生だとか、インターンシップの単位の履修対象でない人もウェルカムです。英語を準備したり、お金の面も含めて準備するという意味において言えば、準備期間が長い方が国際インターンシップではメリットです。そういう意味でも対象学生、対象年次ではなくてもどんどん来てもらいたいです。ただ、事前に準備できなかったから国際インターンシップ行けないというわけではありません。ほとんどの学生は、3年生になった後でインターンシップ推進室に来て、今年の夏に行きたいのですけど、という相談から始まるのが現状です。だから、思い立った時に来てくださいということを伝えたいですね。

■古川 浩規 特任准教授
インターンシップ推進室特任准教授。
電通大を卒業後、官公庁勤務を経て独立し、ベトナムで起業。
「皆さんと国外をつなぐお仕事をしています。」

■大堀 結衣 キャリアカウンセラー
インターンシップ推進室キャリアカウンセラー。
主に国内インターンシップを担当し、学生との面談を実施。
履歴書・エントリーシートの添削などを行っています。
インターンシップ推進室の情報は以下のリンクから↓
インターンシップ関連記事は全4回!!
第1回はこちらから↓
第2回はこちらから↓
第4回はこちらから↓