久野先生へのインタビュー企画 第一週
1984.3 東京工業大学理工学研究科情報科学専攻博士後期課程 単位取得退学 1984.4 東京工業大学理学部情報科学科 助手 1986.3 理学博士(東京工業大学) 1989.4 筑波大学大学院経営システム科学専攻 講師 1990.8 同 助教授 2000.12 同 教授 2016.4 電気通信大学情報理工学研究科 教授, 筑波大学 名誉教授 2022.4 電気通信大学情報理工学研究科 特命教授
久野先生は、2016年に本学教授として就任され、一年次必修科目「コンピュータリテラシ/基礎プログラミングおよび演習」のカリキュラム作成に尽力されました。長年、プログラミング、ユーザーインターフェース、情報教育の分野をご専門とされ、情報の教科書なども執筆されています。詳しくは先生の個人サイトをご覧ください。

Chapter1
学生時代について
久野先生の学生時代について教えてください
自分の学生時代についてですが、学生時代って随分前の頃ですので、自分の良いことしか覚えていないというのはちょっとあります。それでもやはり自分のタイプとしてはいわゆる「良い生徒」でしたね。学校もいろいろ問題とか、悪いところとか言われていますけど、自分には日本の学校は結構合っていて、楽しい学生時代を過ごしました。
どのようにして東京工業大学への進学を決めましたか
僕の出身高校は学芸大附属高校でした。そこで高校3年生の時に初めてミニコン1に触れました。ミニコンを触らせてもらったらすごく面白くて。それまではオーディオか、何かそういう分野に行きたいと思っていました。急にコンピュータがすごく面白いと思うようになり、それで情報科学があるような学校を探して、東工大にあるということで入学しました。
では高校の頃から結構理系だったんですね
理系でしたね。物理が一番得意でしたから。
東京工業大学に入学されてから、どこの研究室に行かれましたか
大学4年の時に研究室が決まったけれども、その時に情報科学科の木村泉先生の研究室に所属しました。そこでいろいろ研究して、自分は耳が悪いので、会社勤めとかは無理と考え、大学勤務の方が絶対いいんじゃないかと思ったので、修士、博士に進みました。
研究分野について
先生の専門分野について、教えてください
さっきお話したように、ミニコンを初めて触って、プログラミングが面白くて情報科学科に進みました。それと関係が深いプログラミング言語、CとかJavaとかあるんですけども、プログラミング言語はとても面白く、一番興味深い研究ということで始めました。
計算機を使っている上で、エディターとか様々なツールがあります。そういうツールを自分で作るのがすごく面白くて、ユーザーインターフェースとしていろいろ工夫できるのが面白いということがありましたので、今言ったプログラミング言語とユーザーインターフェースが結局自分の研究分野となりました。そして、この2つが主な研究分野だったんですけども、終わりの方になって、以前から頼まれ仕事としてやっていたセンター試験の「情報関係基礎」の出題委員とか情報処理学会の初等中等教育委員会とか、そういうところがあったりといううちに、情報教育がメインになったという風な感じです。
先生は主にプログラミングから入られてUI周りの研究をされて、さらに情報教育についても初期から携わられたりしていますよね
終わりの方では情報教育ばかり研究してましたね。
まさしくそれがコンピュータリテラシーとか基礎プログラミングおよび演習(以下”基礎プロ”)につながっていくということでしょうか
もちろんそれはそうですね。内容そのものがコンピュータかどうかというより、プログラミングもそうですし、リテラシーの方もコンピュータが使われている、そういうことがもともと自分の研究の前半でいろいろやっていたのが土台になって情報教育に活きたというのは結果的によかったと思っています。
研究分野で面白いエピソードとか印象に残っていることなどあればお聞かせください
自分で初めの頃はオブジェクト指向言語とかオブジェクト設計とかやっていました。その中でこういうのがあったらどうだろうと自分の先生にお話したけれども、先生からあまりいい反応がなくてやらなかったということがありました。それが、後になったらそういう色々なものが出てきて、あのときにやっていれば今は先駆者になれたなと思ってます。
先生の師事されてた木村先生は結構認知科学の分野を研究されていた先生ですよね
木村先生も初めのうちはやはりコンピュータとか理論とか、あとシステムプログラミング、つまりOSなどに関係する部分のプログラミングとかそういうのがメインだったんですけれども、最後は認知科学とかそのようなものをやっていたという感じですね。だから、僕はだいたい木村先生がシステムプログラムとかやってた終わりの方でした。そういうOSに近いプログラミングが面白くてやっていました。僕と木村先生の研究はそこから後は離れたけどその時は結構面白いことをいろいろ教わったと思っています。
先生の書かれた中で特におすすめの著書や論文はございますでしょうか。
私は著書は多いんですけども、「コンピュータもの」ってしばらくすると古くなるという性質がどうしてもあるので難しいのですけれども、割とその中では「Rubyによる情報科学入門」っていう本がありまして、これはRubyによって情報科学の様々な基本的なアルゴリズムを動かしてみるというものなので、基礎プロの内容の前身にあたるものですけども、この本は自分としては教え方が面白いと思っています。ただ電通大生のみなさんはまあ基礎プロの方をやっているので、そういう意味ではご存じということになってしまいます。それからもう一つは「Javaによるプログラム入門」。やっぱりJavaによるプログラムをどういう風に利用するかというのを考えて書いたのでこれなんかも教えたい。
それからコンピュータリテラシーの内容にちょっと近い内容としては「UNIXによる計算機科学入門」というような関係の本もあります。そういう本もあるんですけど、それはやはり情報リテラシーですね。内容としてはコンピュータリテラシーの前身のようなそういうものですね。どれもやはり内容的には電通大で授業を受けている人は聞いたことがあるようなものですが、授業では時間がやっぱり限られているんですよね。それでいうと本の方がある程度好きなことを書いてるというのがありますよね。
研究室について
先生がどのように研究室を決められたかについてお聞かせください。
学部の授業を大学入って受けましたよね。東工大の場合は、1年は全然コンピュータに関するものがなくて、2年から学科に入って、いろいろあったんです。2年と3年の間の2年間で、いろんな先生の授業を受けたんですけども、その中で、木村先生の内容が一番面白くて、自分の好みに合っていたという感じです。で、木村先生の研究室を第1希望にしたら、無事に配属されたという感じです。そういう意味では電通大の皆さんがいろいろ苦労して競争をしたり、自分の希望するところに入れなかったりということが、あったりして大変だと思いますね。
先生が当時興味を持たれた木村先生の授業というのは、どのような授業でしたか
コンピュータとか、システムを使うとか、そういう部分について、先生がやられていたのでそういう内容ですね。例えば、アセンブリ言語とかその他のプログラム言語とか、OSとかそういう内容なんですけども、その端々にですけどいろんな経験談とか雑談とか、そういうものが僕としては面白かったという感じですね。
先生を見て選ばれたのも結構あるということですね
先生を見て選んだというのは私はそうですね。ただ実際、大学の先生というのは、授業が非常に上手い先生もいれば、授業は下手だけど研究は強いとかいう先生もいるわけですから、授業が上手いというだけで選ぶのがいいかどうかはちょっと分からないですけども、木村先生は非常に授業も面白くて、研究内容はさっき言ったように最初のうちは僕のやりたいことが非常に大きくあっていたのでよかった。その後は少し離れてしまったけれど。
今、研究室選びを悩んでいる学生が多分たくさんいると思うのですが、どのように決めればよいでしょうか
私が言えることは、多くの先生と直接話をすること。そういうのが非常に大事だと思うんですね。授業の時間だとあんまり先生と話をするというのは機会がないじゃないですか。ですから、所属を考える間になるべく多くの先生と話をして、実際にどういう研究なのかとか、どういうところが大変なのかとか、どういうようなお話をするのかとか、そういうことは先生方で全然違いますから、ぜひいっぱい先生と話をするのをお勧めします。
先生も木村先生も、木村先生以外にもたくさんの先生とお話されたんですか。
僕の配属期間中に木村先生は在外研究期間で日本にいなかったんです。だから僕の場合は先生と話はできなくて、授業だけで選んだんですけども、できれば話をした方がいいのは絶対そうだと思います。
前編は全三週間にわたってインタビュー記事を公開予定です!
今回は一週目ですので、二週目もご覧いただけると幸いです!
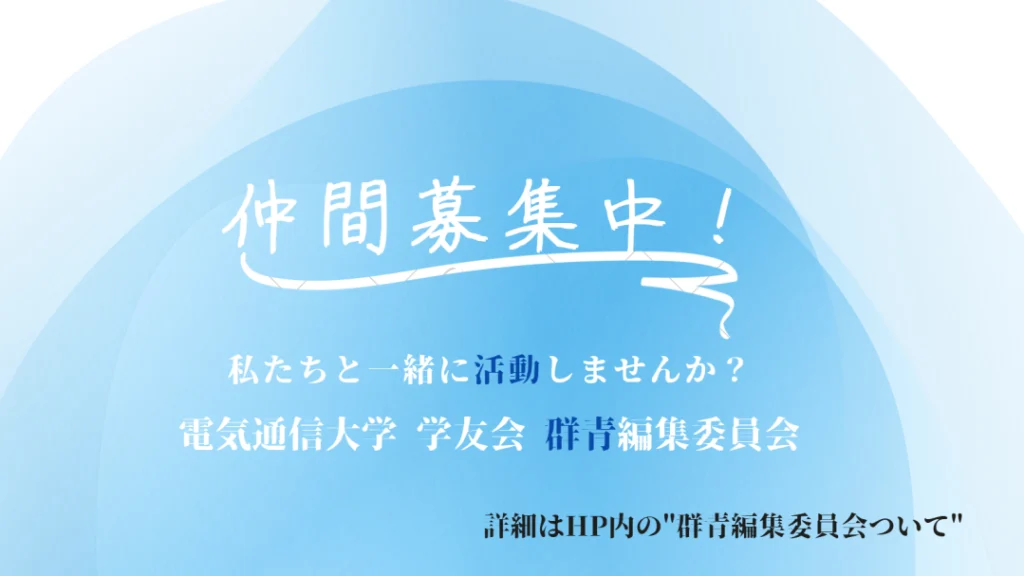
- ミニコンはミニコンピュータの略称であり、1960年代から1980年代に使われた中規模のコンピュータで、メインフレームとPCの中間に位置する。安価で小型ながら、複数ユーザーの同時利用や中規模の処理が可能で、企業や研究機関で広く活躍した。 ↩︎

