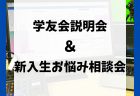田野学長インタビュー ~新入生にむけて~
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!
今回の記事では、入学生の皆さんに電気通信大学をより深く知っていただき、学生生活をより良いものにしていただくために田野 俊一学長に赤裸々にお話をいただきました。
在校生の方にも興味深い内容だと思いますので、ぜひご覧ください!
また、去年の11月に学生との交流ためにオープントークを開催されています。こちらも合わせてご覧いただけると更に理解が深まるかと思います!
https://office.uec.ac.jp/president/open-talk/ (学内ネットワーク限定)

(写真提供:写真研究部)
田野 俊一 学長
1958年生まれ、宮崎県出身。1981年3月、東京工業大学制御工学科を卒業。
1983年3月、東京工業大学大学院総合理工学研究科システム科学専攻修士課程を修了。
専門は制御、ファジィ理論、人工知能、システム科学など。
本学(電気通信大学)には、1996年に電気通信大学大学院情報システム学研究科助教授として着任。
2008年に副学長に就任し、その後、学長補佐、研究科長、学術院長などを歴任。
2020年に学長に就任し、現在は2期目を務めている。
リサージュ図形と日本をつなぐ大学、電通大
うちの校章に採用されているリサージュ図形は、東日本50Hz・西日本60Hzの電源周波数に対応しています。日本は周波数的に分断されているけれども、うちの大学はそれをつなぐ・仲良くする大学を目指しています。
そのため、日本で唯一大学名に地名がついていない学部を持つ国立大学で、「日本全国に開かれた大学を造る」という理念を体現しています。1
「尖ったものを好む」遺伝子とオタク文化
電通大の起源は、100年前の無線電信講習所に遡ります。当時、最先端であった無線電信を広めるために設立され、紡績を目的とした他の大学とは異なる、独自の歴史を持っています。無線電信に使用されるモールス信号は、いわば人力によるデジタル信号処理であり、その当時から「最先端の技術で世の中を良くしていこう」という理念がありました。
そのような特殊なものを好む遺伝子があり、国立大学としては最初期に経営学科や電子計算機学科を新設しました。
ただ、そのような中で、外部の講師が来ると、モールス信号でカンニングできてしまっていたんですよね(笑)。外部の人にはわからないような文化が、今のオタク文化につながっていると、今考えると思います(笑)。
他大学と比べたときの電通大について
電通大の研究レベルは非常に高く、全国でわずか19の大学しか選ばれなかった「研究大学強化促進事業2」にも選ばれています。
また、教育の面でも優れた実績を持ち、著名400社の実就職率ランキングで8位を獲得する3など、高い評価を受けています。
電通大がこうした成果を上げていることを、ぜひ多くの人に知ってもらいたいです。
電通大の唯一の目標:「共創進化スマート社会」
電通大が主導する「共創進化スマート社会」は、単に言葉を並べただけではなくて具体的なビジョンがあるんです。
実現するために3つの箱を考えていて、
1つ目の箱が、データと機能をネットワーク化することです。世界中の全てのデータと機能がネットワークで繋がり、API等を通じて地球の裏側の温度計の情報取得や発電機の制御などができることを考えています。
2つ目の箱が、AIによる最適化です。データや機能をたくさん入手したとしても、人間には増えすぎて扱いきれなくなるでしょう。そのため、AIがデータを解析し、最適な制御方法を見つけ出すことが必要です。例えば人数変化や気候の変化に応じたエアコン調整をAIが自動的に行うなどです。
3つ目の箱が、社会への実装とそのシュミレーションです。AIが最適化方法を見つけたとしても、それが安全かどうか確認が必要です。そのため、社会に実装する前にシミュレーションを行い安全性を確認します。
これらの3つの箱を持って、リアルタイムで進化していく社会というのを目指しています。逆に電通大はこの「共創進化スマート社会」しか目指しません。4
新棟:エネルギー棟について
J-PEAKSという文部科学省の事業に西東京3大学(電通大、外語大、農工大)で応募し、採択されました。その際に、電通大は「エネルギーの持続性」を標榜しました。
その事業のお金で建てられたのが「エネルギー棟」です。この施設では、エネルギー+ICTを研究する拠点として使用されることを期待していて、外壁には円筒形の太陽光発電器を外壁に並べたものにする予定です。その電力で地域の人も充電できるようにするとか、そういうことも考えています。
エネルギー棟は3階建てで、1階は現在のB棟ロビーのような学生や留学生が自由に利用できるオープンスペースとして設計されています。草が生い茂っていたところを整備して広場とかウッドデッキとか学生が集まりやすい場所にする予定です。建物自体は3月の末には完成の予定ですが、周辺の整備とかに半年かかって今年の秋頃に完成のお披露目会をする予定です。
西9号館もおんなじ感じで作って、夜はいい感じなんだよね(笑)。かっこいい場所を作ったので学生のみんなも是非行ってみてほしいです。

Dx2プログラム(データサイエンス・デザイン思考)について
データサイエンスが世の中で流行したことを受け、「これを作らなければ」と考え、新設しました。
しかし、データサイエンスだけでは不十分で、「どのようにすれば人間のためになるのか」を考えるデザイン思考的な視点も重要です。そこで、「D: データサイエンス・D: デザイン思考」として、当初は D.D と呼んでいました。
すると、ある人が「Dが2つだから Dx2(でんつー) じゃん!」と気づき、それがきっかけでDx2プログラムとして宣伝されることになりました。
Dx2プログラムのすごい点は、都内にある国立大学は「民業圧迫になる」との理由で学部定員を増やせないにもかかわらず、世の中で情報を扱える人材が求められていることを踏まえ、特例として東工大と電通大のみ定員増が認められたことです。これは本当に「異例」なことだと感じています。
AIと私達の向き合い方について ~「自分の頭の中が勝負」~
うちの大学は、他の大学と違って、生成AIを「危ないから使わないでください」と禁止することはしていません。AIを研究する大学である以上、それを禁止するのではなく、むしろ活用しながらAIの限界を知り、正しく使いこなせるようになってほしいと考えています。AIが世の中にあふれる時代はすぐに訪れるでしょう。だからこそ、使わないと損だと思っています。
昔は、学生のレポートを読んだときに「本当に日本人が書いた文章なのか?」と思うこともありましたが、今はすべてカンペキな文章なんですよね(笑)。ただ、問題は使い方です。出力されたものをそのまま使うのではなく、一度自分の中に落とし込み、しっかりと理解することを心がけてほしいと思います。
では、AIが賢くなってきたこの世の中で、人間には何が残るのでしょうか? それは「直感」です。LLM(大規模言語モデル)は世界中の過去の文献を学び、それを組み合わせて新たな文章を生成していますが、そこから本当に新しいものを生み出すのは難しい。一方で、人間には五感をベースとした「直感」があり、それがあるからこそ新しいアイデアを生み出すことができます。しかし、直感を働かせるためには、頭の中に覚えていることを組み合わせ、融合させる必要があります。
Google検索やChatGPTが普及した現代では、情報は簡単に手に入ります。しかし、それだけでは不十分で、頭の中にしっかり知識を蓄え、それを自在に使えることが重要です。こんな時代だからこそ、「頭の中が勝負」なのです。
- 本学HP:校章・コミュニケーションマークを参照 ↩︎
- 文部科学省:令和3年度「研究大学強化促進事業」のフォローアップについてを参照 ↩︎
- 東洋オンライン:最新!「有名企業への就職に強い大学」トップ200校を参照 ↩︎
- 本学HP:UECビジョン ~beyond 2020~を参照 ↩︎
次のページでは、「新入生に向けたメッセージ」をお聞きしました!